世界農業遺産とは
世界農業遺産(GIAHS)は、社会や環境に適応しながら何世代にもわたり継承されてきた独自性のある伝統的な農林水産業が、文化、ランドスケープ、シースケープ、農業生物多様性などと相互に関連し、国際連合食糧農業機関(FAO)によって認定されるものです。
世界で26ヶ国86地域、日本では15地域が認定されています(令和6年1月12日更新)
日本初の登録
2011年、新潟県佐渡市のトキと水田環境、そして石川県能登地方の里山・里海が日本で最初に登録されました。
和歌山県みなべ町・田辺市が認定
2015年12月に和歌山県のみなべ・田辺の梅システムが世界農業遺産に認定されました。
みなべ・田辺の梅システム

みなべ・田辺の梅システムは、養分に乏しく礫質で崩れやすい斜面を利用し、
400年以上にわたり高品質な梅を生産してきた農業システムです。
里山の斜面を活かし、薪炭林を残すことで水源涵養や崩落防止の機能を持たせ、
薪炭林に住むニホンミツバチを活用した梅の受粉、遺伝子資源の保護、
薪炭林のウバメガシを使った製炭など、地域資源を有効に活用しています。
紀州備長炭との関連
農家のやまさきが主に梅を生産している田辺市秋津川地域が紀州備長炭の発祥の地とされています。
農家のやまさき は梅を生産しつつ、畑の斜面や境界線にウバメガシを植林しています。
成長したウバメガシは炭焼き職人によって間伐され、これが梅農家と炭焼き職人のwin-winの関係を築いています。
課題と取り組み
梅農家の高齢化と急斜面の耕作放棄が進んでいますが、近年では再び薪炭林としての再生活動が行われています。
これにより、管理された里山が保護され、生物多様性や土砂災害抑制に貢献しています。
梅システムのこれから
梅と炭とミツバチ、そして地域の人々との深い関わりが形成するこの農業体系が、世界農業遺産に認定された理由です。肩書だけでなく、地域の宝である南高梅を広く知ってもらい、次の世代に繋げていくために、この取り組みを積極的に発信し、理解を深めていくことが重要です。



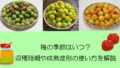
コメント